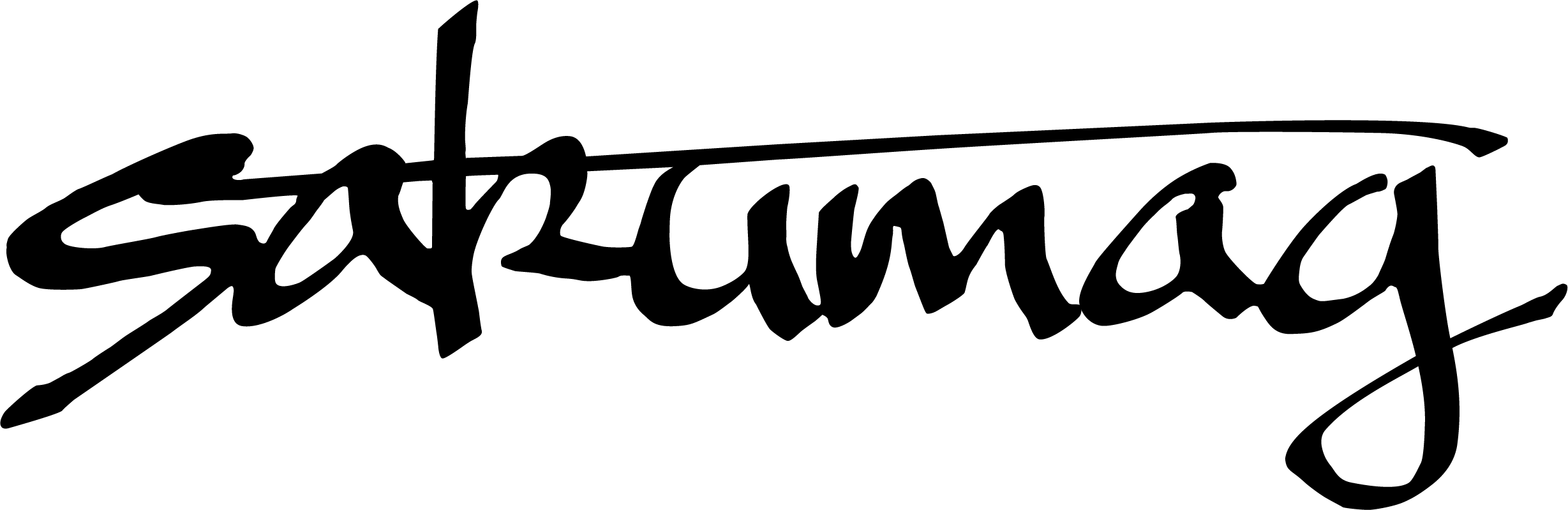若林恵:あなたは音楽 Mitski「Be the Cowboy」のこと

文章:若林恵 Kei Wakabayashi
『初恋』というタイトルがつけられたニューアルバムのリリースを直前に控えた女性音楽家のインタビューをさせていただくことになり、事前に送られてきた音源を繰り返し聴いた。タイトルが示す通り、そのアルバムには文字通り「恋」や、もっと広い意味での「愛」がたくさん歌われていた。
ラブソングが概ね、男女の関係について歌われるものであったり、もっと広義のものとして同性の人物や自分の親や子がそこに含まれたとしても、そこで「あなた」という歌詞が出てきたら、それは当然、恋や愛の対象であるところの「人」を指していると誰しもが思うはずだ。
けれども、そのアーティストに限っては、どういう理由なのか定かではないが、そこで歌われる「あなた」が人として像を結ばないという感覚があった。ここで言われている「あなた」は、何か別のものを指しているのではないか。彼女はインタビューの当日、自身が抱える孤独と欠落について多くを語った。「私には『社会』ってものがないんです」。そう語る彼女にとって「人」は、彼女が最も深くコミットする対象ではないのかもしれない。
「歌のなかで歌われている『あなた』は、実際は『音楽』のことではないですか」
それが、おそらく、その日のインタビューでした一番冴えた質問のつもりだったが、多くの人にしてみればナンセンスなものでしかなかったかもしれない。恋愛の歌のなかで歌われてる「あなた」は「人」に決まってる。歌の解釈は、もちろん聴き手の自由だ。その自由のなかで、聴き手は銘々、歌に自分の物語を重ねあわせ「あなた」の語に具体的な誰かをあてはめる。そこになんの間違いがあろう。
ところが、自分が発した疑問があながち的外れとばかり言えないことが、そのインタビューから数カ月後、意外なところから判明する。
「私の歌のなかで歌われている『You』は、『音楽』という漠然とした概念のことを指している場合が結構あります」
あるウェブ記事を読んでいたら、不意にそんなことばに出くわした。ことばの主は、シンガーソングライターのMitskiだった。
リリース前から大きな期待と注目を集めていた5作目のアルバム『Be the Cowboy』は、リリースされるや否や「Pitchfork」で8.8点の高得点を得た。彼女が上記の発言をしたのは、リリースと同時にPitchforkに掲載された「Don't Cry for Mitski」という記事のなかでだった。
*
本名、ミヤワキ・ミツキ。インディロックの救世主とも目される27歳の女性音楽家は、日本生まれだが、親の転勤の都合で引っ越しを繰り返し、コンゴ共和国やトルコ、そしてアメリカを転々としながら育った。彼女はインタビューのなかで、そうした体験が人と関係を築くことをとても困難なものにしたと語っている。
「どうせ来年にはいなくなるので、友達もつくりませんでした。仲良くしたところで意味がないんです。だからどこに行っても、周りと馴染まない変人と思われていました」
彼女はどこにいてもつねに孤独なエイリアンだった。それでも、そんな彼女がただひとつコミットできる対象があった。それが音楽だった。
「音楽をつくり続けることができるのであれば、私はどんなことを犠牲にしても構わないと思っています。自分自身も含めて。それがどんな苦痛を伴うとしても、音楽家でいられるなら構いません」
Mitskiは、デビューしたときから、孤独や不信や欠落や嫌悪といったものを、むき出しの激しさで歌ってきた。デビュー当時はピアノを自分のメインの楽器としてきたが、2014年、3作目のアルバム『 Bury Me at Makeout Creek』で初めてギターを手にする。言い知れぬ怒りと苛立ちをぶつけるように歪んだギターを掻き毟り、その轟音に乗って吐き出すように歌をぶちまける。その姿は、ときに生々しく、うっかり目を伏せてしまうほどにあられもない。
けれども、それが、もちろん、彼女が支持を集めてきた理由でもある。
「あなたの音楽を聴いて泣きました。まるで日記のようで、とてもパーソナルですから」
Mitskiのファンは、そうやって彼女に共感し、サポートする。自分の孤独や失恋や自己嫌悪などの経験を歌に投影し、涙を流す。けれども、Mitskiは、そんなリスナーには極めて冷淡だ。
「そりゃあ、たしかにわたしの音楽はパーソナルです。でも、そのコメントは、それ自体ジェンダー化されたものですよ。SNS上に『次のアルバムで泣くのが楽しみ!』なんてコメントを見かけると、『申し訳ないけど、次のは泣けないよ』って心のうちで思うんです」
US版の「GQ」に掲載された記事では、彼女は、「あなたの音楽のこういうところが好きです」とファンに言われたら、指摘されたことを以後二度としないよう心に刻むのだと語っている。そして実際、彼女がリリースした「次のアルバム」は、大方の予想を大幅に裏切る作品となった。ざらついたインディロックサウンドはなりを潜め、アルバム全体が磨き上げられたクリーンでカラフルなサウンドに彩られ、曲調もバラエティに富み、なかにはダンサブルとさえ言えそうなディスコチューンだってある。
*
彼女がことさら天邪鬼な人間であるというわけではないだろう。彼女がやっていることと、リスナーが彼女がやっていると思っていることの間には、ただ大きなズレがあるだけだ。彼女がある男性に恋い焦がれる歌を歌っているとみんなが思っているとき、彼女は音楽に恋い焦がれる歌を歌っている。話がすれ違うのも無理はない。アルバムのオープニングナンバー「Geyser」はこんな歌詞で幕を開ける。
あなたはわたしのナンバーワン
わたしが欲しいのはあなただけ
わたしに差し伸べられた手を
あなたはすべて拒絶する
わたしにはあなたしかいない
わたしにはあなたしかいない
だから差し伸べられた手を
わたしはすべて拒絶し続ける
Mitskiの言に従って、「あなた」を「音楽」に置き換えて読んでみたらどうだろう。ある男とどうしても別れることのできない女性の心情を歌ったように見える歌は、音楽と心中することもいとわない音楽家の悲壮な覚悟を歌ったものへと変容する。そして、この歌を歌うMitskiも、女心の暗さを自ら体現し、その機微を巧みに描きだす達人から、かつて音楽によって得た癒しや救いを執拗に追い求め、それを一生かけて追究する求道者へと姿を変える。
そのどちらの存在に、わたしたちはより共感しうるのだろう。
個人的なことを言ってしまえば、いくら真に迫ったものとして恋の顛末を歌われたところで、それに真から共感することは、どうにもできそうにない。性別の違いはもとよりあるし、彼女の特殊な経験から出た人間関係の特殊さを、ほんとうに我が物として感じることができるのかは疑わしい。けれども、彼女が音楽に救いを見出し、それにすがるようにして穏やかならぬ内面生活を生きてきたこと、そして、そうであるからこそ、彼女の音楽が音楽という対象に向けられたラブソングになっているという事実には、むしろ心を打たれるものがある。なぜって、いまでも自分が音楽を聴き続ける理由は、程度の差こそあれ、音楽にMitskiが求めたようななにかを求め続けてのことだからだ。
ある理由から音楽というものに、それまでの生活の中で味わうことのなかったときめきや感情のざわめきを感じ、それがときに救いとなり、癒しとなるような体験があればこそ、人は音楽を、いや音楽に限らず、小説だったり、絵画だったり、映画だったり、といったものを、継続して求め続けることができる。音楽そのものが自分にとってこの上もなく大事でない人は音楽をやる理由なんかないだろうし、音楽のなかに特別な瞬間を得た体験をもたない人が音楽という形式になにかを求め続け、聴き続ける理由もない。表現する者とそれを受け取る者が交錯しうるのは、まずはその前提のなかにおいてなのではないのだろうか。
たとえば、自分がtofubeatsという音楽家が本当に好きなのは彼が一貫して自分を救ってくれたはずの「音楽」に思いをめぐらせ、それを音楽にしているからだ。tofubeatsという人がどんな恋愛をしているのか知らないし興味もないけれど、彼がどういうふうに音楽というものに恋に落ち、どういうふうにそれに悦ばされたり、傷ついたり、悩まされたりしてきたかが、音楽を聴いていると、なんだかとてもよくわかる気がする。
*
Mitskiと冒頭で触れた音楽家は、ともに「First Love」という曲を書いている。それが実際の人との恋愛を歌ったものなのかどうなのかは知るよしもない。けれども、そこで歌われる「あなた/You」が音楽そのものを表している前提で、もう一度それを聴き直してみることは許される。「初恋」を「音楽そのものへの初恋」と理解したなら、彼女たちが歩んできた凄みのある人生も、これまでとは違ったものに感じられるかもしれない。こんなにまで激しく音楽に恋い焦がれ、信じ続けることができる人がいるのか。そう感じることを通して、聴き手は改めて音楽の力を信じることができる。
Mitskiの音楽はたしかに泣けるだろう。けれども、その涙の本当の理由は大方が思っているのとは、ちょっと違うところに宿っている。その音楽を通して「音楽ってものがあってよかった」と感じるところに、まずその理由は宿るはずなのだ。