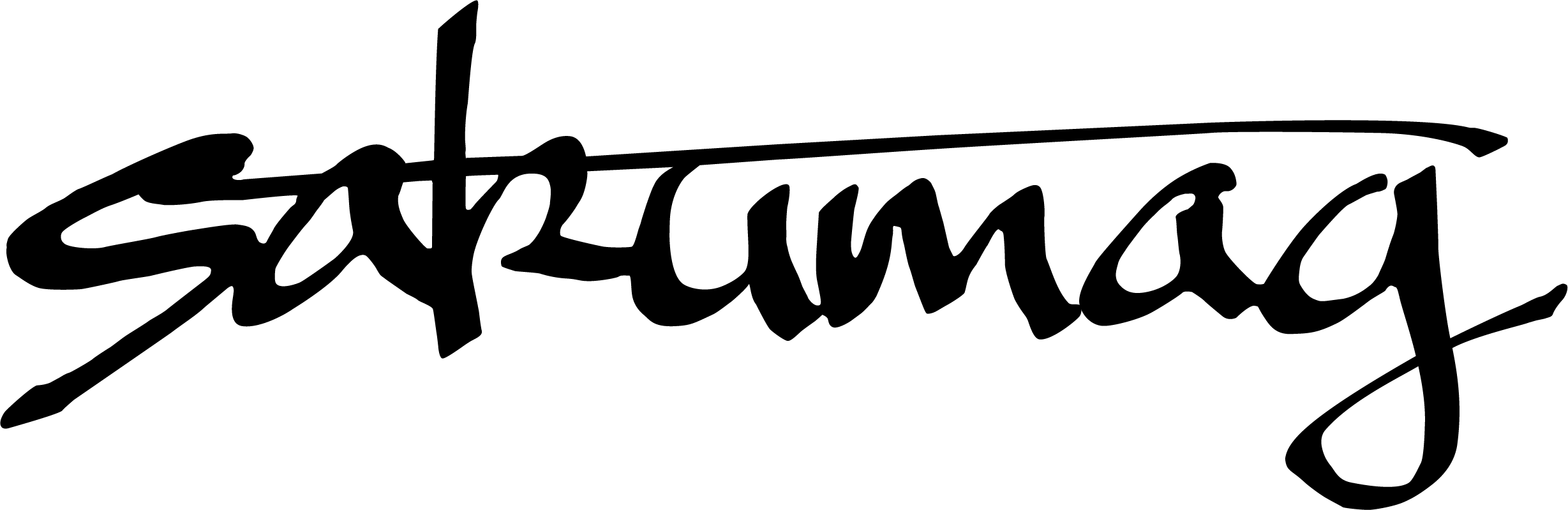Weekly Sakumag Sample 06.01.2020

歴史を見ても、クライシスというものは、変革のきっかけとして機能してきたわけで、となるとこれだけの好機に変われないのだとしたら、よっぽど終わっているということになるが、変わろうとする社会に抵抗する力もまた強いことは否定できない。ウィルスによる死者数が日々、確実に数を重ねているのにもかかわらず、経済再開を急いでさらに感染者を増やしている保守州で、再び感染者数が跳ね上がっている。失業率が急上昇し、食糧を確保できない市民の数がどんどん増えている(ニューヨークでは4人にひとり)にもかかわらず、相変わらず株式市場が活発なこともそうだし、ブルックリンの不動産売買がスーパーリッチのお買い物によって、史上最高の取引高を記録したこともそうだ。
ミネアポリスの警察官が「息ができない」と助けを求める声を無視して、ジョージ・フロイドさんという黒人男性の首に膝をかけ続け、殺した映像が拡散されたことで、ゴーストタウン化していた都会の様相を一気に変えた。ただでさえ、コロナウィルスの感染者数や死者数が、アフリカ系アメリカ人に偏っているという不平等が問題になっていたタイミングで、丸腰の黒人がまた一人、死ぬ理由なく死んだことで、人々が抗議のためにストリートに飛び出した。極右の白人至上主義団体が人員を送り込んだ。デモが起き、警察と衝突すれば、そこには略奪を目的とする人々もやってくる。ソーホーに暮らす友人から、シャネルストアに押し入る集団の映像が送られてきた。
今回の映像を見て、ショックを受けた人たちはこのサイトを見てほしい。アメリカの警察によるバイオレンスの現状だ。#blacklivesmatterについてはこれまでも度々取り上げてきたが、どれだけ平和な抗議活動を続けたところでこうした事件がなくならないことに、アクティビストたちはうんざりしている。そしてその過程で、抗議運動をする人たちと、火事場泥棒が混同される。
今回の事件の特色は、各地の警察関係者の中からも、ミネアポリスの事件を非難したり、デモとの団結を表現する声が強いことだ。TwitterやNIKE、Netflixが早々に#blacklivesmatterとの団結を表明したことも覚えておこう。
OxfamがWHOの加盟国に呼びかけている世界共通のワクチン開発に、アメリカが参加しない意向を示している。トランプが表明しているWHO脱退が法的に可能かどうかはまだ明らかではないが、パンデミックは、グローバルな問題にもかかわらず、自国中心主義のおかげで、いつのまにか医療が国家安全保障問題になってしまった。日本政府はこれに気がついているだろうか。ワクチンの開発において、頭ひとつ出ている感のある中国が、このタイミングで、中国が国家安全法を導入するという。本来なら2045年までは保障されていたはずの香港の自治がいよいよ危ない。コロナウィルスによって、中国内の国民感情が悪化し、中国政府による香港弾圧が減速するのではと淡い期待を抱いていたが、今までのところ、そうはなっていない。
アメリカでは、11月の選挙に向けてデジタル選挙運動が活発になってきた。大統領選挙もさることながら、注目されているのは、上院選である。アリゾナやケンタッキーなど、これまでがっつり赤だった州で民主党の候補が追い上げている。特に保守派の政策実現と保守派判事の任命を粛々と進めてきたミッチ・マコネル上院院内総務の議席は注目度が高い。前回の大統領選挙ではフェイクニュースに一方的にやられた感のある民主党サイドではあるが、いま、フェイスブックでトランプという検索語をかけるとトップの上位を占める率の高いmeme makerがいる。メキシコ移民の二人兄弟が運営しているというのだが、なかなかよくできている。このビデオのDIY感もたまらない。ようやく左派は、右派の狡猾なデジタル戦略に対抗するのに有効な声を手に入れたのかもしれない。
今、早急に問題になっているのは、11月の大統領選挙(および地方選挙)の郵便投票を可能にする整備づくりである。トランプ大統領や、投票率が低いほうが強い共和党は、「不正投票のリスク」を理由に反対しているために、その攻防が注目される。ここで状況を複雑にするのは、郵政公社の経営不振である。コロナウィルスによって激しい打撃を受けたUPSPS(郵政公社)は、このままいくと秋にはデフォルトに陥るだろう。そしてトランプはその救済を拒否している。背景には、自分に批判的なワシントン・ポストを所有するAmazonのジェフ・ベゾスへの敵対心がある。
今、もうひとつこれまでになく盛り上がっているのは、労働運動である。社会の大半がウィルスを恐れて外に出ないなか、前線で働く人たちへの依存度は高く、だからこそこのクライシスを労働運動の最大のチャンスだととらえる向きは少なくない。
コロナウィルスの危機が始まって、前線で働く人たちのための危機管理や待遇がにわかに注目された。進んで安全対策を発表したところもあれば、Amazonやクラスタ化して閉鎖になった肉工場のように、社内のウィッスルブロワーから「安全対策が十分でない」との告発があった企業もあった。Amazonは、組合を組織しようとした従業員を解雇して、ますますろくでなし街道をまっしぐらである。
今週、大手スーパーのKrogerが話題になっていた。コロナウィルス時代に入って、危険をおかして前線で働くスタッフの時給を2ドル上げる措置を取っていたのだが、「経済再開」が始まると同時に、彼らの給料を通常に戻そうとして叩かれていたうえに、今日は、手続き上のミスで、底上げされた金額を得た従業員たちに「差額を返せ」と指示した手紙がすっぱ抜かれて、さらに叩かれていた。騒ぎになったために、回収するという意向は撤回したそうだ。ちなみにKrogerのCEOの昨年の給料は、1400万ドルだったという。
所得格差解消は、AOC(アレクサンドラ・オカシオ・コルテス)世代が提唱するグリーン・ニュー・ディールの大きな柱のひとつでもあるし、ミレニアル世代のバイコッターたちにとっても最大の関心事のひとつである。Teen Vogueが、1918年にスペイン風邪が流行ったときにも労働運動が進んだ、という記事を出していて、Vogue Businessが、ファッション業界のフリーランサーは組合化するべきか、という記事を出している。時代の潮目が変わったのだと感じる。
コロナウィルスのロックダウンが始まった頃、食糧業界から「食材は大丈夫です」というメッセージが発信されていたが、あれから2ヶ月、状況は劇的に変わった。外食産業に食材を提供していた業者は、商品の買い手を失い、たくさんの食糧が廃棄処分された。食肉工場でクラスターが発生し、工場が営業を続けることができなくなったために、大量の動物が屠殺されることになった。一方、失業者が増え、貧困が深刻化する中で、子供の5人に1人が食べられない状態に陥っている。食関係の非営利団体が、外食業界に供給するための食糧のルートを変えて、飢えている人に届ける努力をしているが、とても間に合わない。
コロナウィルスが登場する以前から、食のサプライチェーンが肥大しすぎて、また産業化が進みすぎて、たくさんの無駄を生み出していること、またそれが環境に負担をかけていることなどは、専門家たちによってたびたび指摘されてきた。そして今、食肉工場から始まった生産中止が食肉のサプライチェーン全体を脅かす可能性すら取り沙汰されるようになった。
こんな状況に、解決策はあるのだろうか。食を専門にする作家マイケル・ポーラン(5月26日には、サイケデリックをテーマとした「幻覚剤は役に立つのか」が早川書房から刊行したばかり。必読)の文章がその危機的状況を解析しているが、結局のところ、脱産業化というラディカルな解決策でしか解決できない可能性がある。そんなことができるのだろうか?と考えているうちに、季節でないものがスーパーで売られている、という今までまったく当たり前だった状況が、むしろ異常だったのだということに気がつく。
ここから30分くらいのところに住んでいる知人は、自分が食べる野菜はすべて自分で育てている。卵用に鶏を飼っているが、肉は食べない。外から買うのは穀物と調味料くらいだ。冬場は、夏のうちに冷凍しておいた野菜を食べる。こういう人の生活は鉄板だ。ワシントン・ポストが鶏の飼育法についての記事を出していたことを見ても、自給自足への欲求が高まっていることは間違いない。
誰もがすぐにそういうことに挑戦できるわけではない。けれど、サプライチェーンの仕組みと現状の問題を考えると、ひとつの野菜を作る農家と、その野菜を手にする自分との間に存在するプレイヤーは少ないに越したことはない。おまけに、食材の作り手と関係を作っておけば、より自分の食料確保は安定する。ローカルのサプライヤーは安定しているのだ。
東京のように自給率の低い都会やローカルの業者の乏しい土地でも、それなりの工夫はできる。今回のクライシスの初期、Amazon傘下のホールフーズや大手スーパーに長蛇の列ができたり、オンラインのデリバリーがパンク状態になったりした一方で、小規模なグルメ、オーガニック商店は安定していた。オンラインでも、定額の会費を払うことで食材や調味料へのアクセスを確保するメンバーシップ制のマーケットや、肉・魚・ワインなどのサブスク・サービスが次々と登場している。「ここなら安心」と思える業者を知っておくことの大切さを学んだ。
ところで、肉のサプライチェーンがいつ崩壊してもおかしくないと言われるなか、フェイクミート市場はますます伸びている。アメリカの食生活のなかで肉が占める場所は小さくない。平均するとアメリカの成人は、1日ひとりあたり、9オンス(255グラム)の肉を食べるという。だからこそ、トランプ大統領が、肉業界を「決定的に重要」指定して、食肉の生産を守ろうとしているわけだ。ところが、若者の肉離れは顕著である。環境意識の高さも手伝って、25~34歳からの若者の、4人が1人にベジタリアンかヴィーガンだというデータがある。そして、ビヨンド・ミートやインポッシブル・バーガーといった大手だけでなく、「肉もどき」を提供するメーカーは元気に増え続けている。
ところで、消費者たちが食糧を大切にするようになって、家庭からの食糧廃棄が減っているという。やっぱり自分の中の発見できる意識改革が多くの人のなかで起きているのだ。
ロックダウンの初期の頃に、こんなに空気がきれいになって山が見えるようになったよ、とか、動物たちがのびのびしてるよ、というレポートが多々出ていて、資本主義が強制的にブレーキをかけられているのだな、などとほっこりしていたのもつかの間、科学的なデータが出てくると、やはり、ことはそこまで単純ではないのだということがよくわかる。
ラジオ局のNPRがまとめたデータを見ると、これだけ大幅に経済活動が縮小しても、実際、オゾンのレベルがそこまで削減していない。このコロナによって偶発的に与えられた「実験」によってわかったことには、空気汚染はたしかに軽減しているが、だいたいの地域においては最大で15%程度しか減っておらず、ピッツバーグやヒューストンのようにエネルギーを生産している地域や、LAのように港町で大型トラックの交通量が多い地域では、軽減の幅はより小さい。
ということはやはり、道はクリーンエネルギーへの転換しかないということである。わかっちゃいたけど、コロナのおかげで、これまではあくまでも仮想でしかなかった「経済活動を縮小した場合」のシナリオの答えが出てしまった。
家で仕事をできる人たちのWFH(ワーク・フロム・ホーム)が始まって3ヶ月近くが経った。個人的には、自分も含めて、社会全体的に仕事のコミュニケーションがいつもより若干スローな気がするのだが、一般的には、世の中の生産性は、下がるどころかむしろ上がっているという。
社員を自宅で働かせても生産性が落ちないことがわかってしまえば、オフィスを持つことの意味が変容してくる。すでに、Twitter、ナスダックのように、WFH(ワーク・フロム・ホーム)を恒常的なオプションとして従業員に提案することを発表している会社もある。フェイスブックのマーク・ザッカーバーグは、自宅勤務は取り入れるけれども、それにあわせて給料を調整する可能性がある、と語っている。今の時点で、長期的な自宅勤務にコミットしていない会社も、年内は職場には戻れないという構えのところが多い。こうしたことが、職場空間をこれからどう変えていくのだろうか。これが「オフィスの終焉」につながるのかどうかがホットなトピックのひとつになっている。
しかし、その未来を考える前に、今、問題になっているのは、オフィスを含めた商業不動産の短期的な未来である。住宅の家賃の支払い以上に、商業家賃を払えないビジネスが増えている。商業家賃が支払われないと、家主によるローンの支払いや固定資産税の徴集にも支障が出てくる。となると、今、コロナによってただでさえ圧迫されている州・自治体の財政はますます追い込まれる。
トランジションの痛みはまだまだ続きそうである。